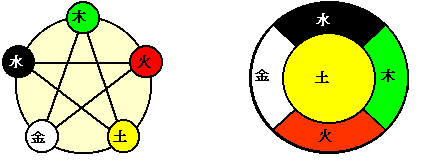木火土金水の間に存在する相生と相剋の関係の発生原理について考えます。
例えば相生は一般的にはつぎのような例を引いて説明されています。例えですから木は本来の「もく」ではなく、「き」と読ませています。
◎相生
木生火 木(き)は燃える。即ち火(ひ)を生ず。
火生土 火(ひ)は燃えて灰になる。即ち土(つち)を生ず。
土生金 土(つち)は金(かね)を含む。即ち土は金を生ず。
金生水 金(かね)には水(みず)が付く。即ち金は水を生ず。
水生木 水は木を育てる。即ち水生木。
以上の説明は、五行が季節の代名詞であることを理解すれば一つの方便であることがわかります。季節は順に行(めぐ)りますから「次にくる」という意味で「生」と表します。
即ち、「木生火」というのは「春の次には夏がくる」という意味を示しています。隣り合う季節は「生」で表し(「反生」という用語もあります)、隣り合わない関係を「剋」と表します。そして「生」は自然の変化に順じているという意味で「吉」といい、「剋」は自然の順序にないものであるので「凶」とします。
木火土金水の五行のみの場合の生剋と吉凶の意味は以上のとおりです。なお、この五行のみの生剋で吉凶判断する方法は姓名学に取り入れているところがあり、氏名の字画数とともに秘伝として応用されています。